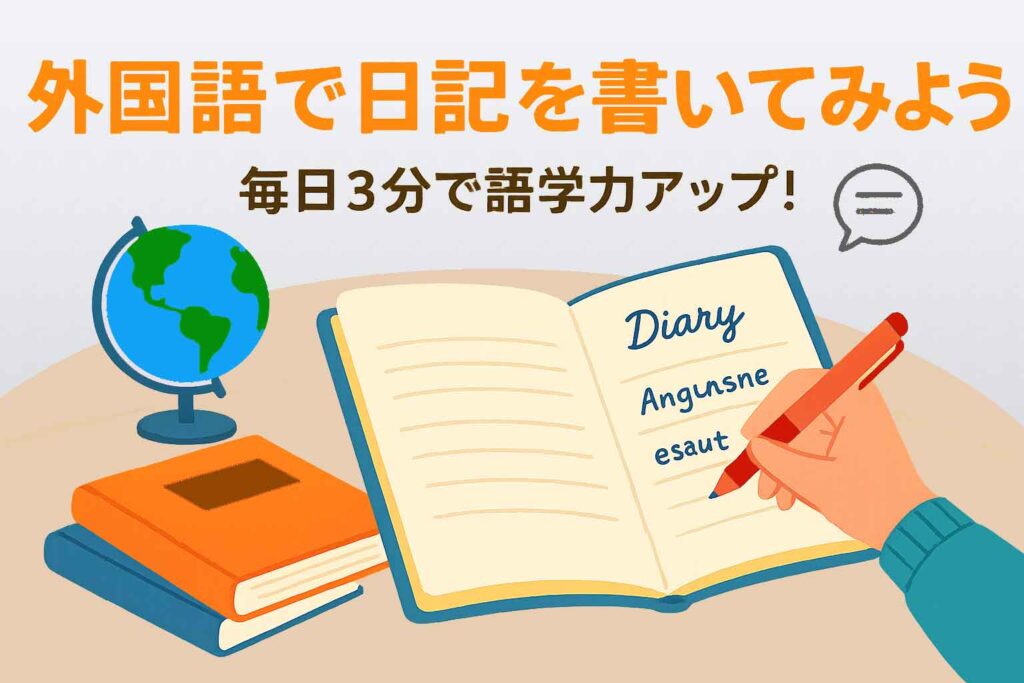外国語を学ぶことは母国語を学ぶこと― ゲーテの言葉から考える
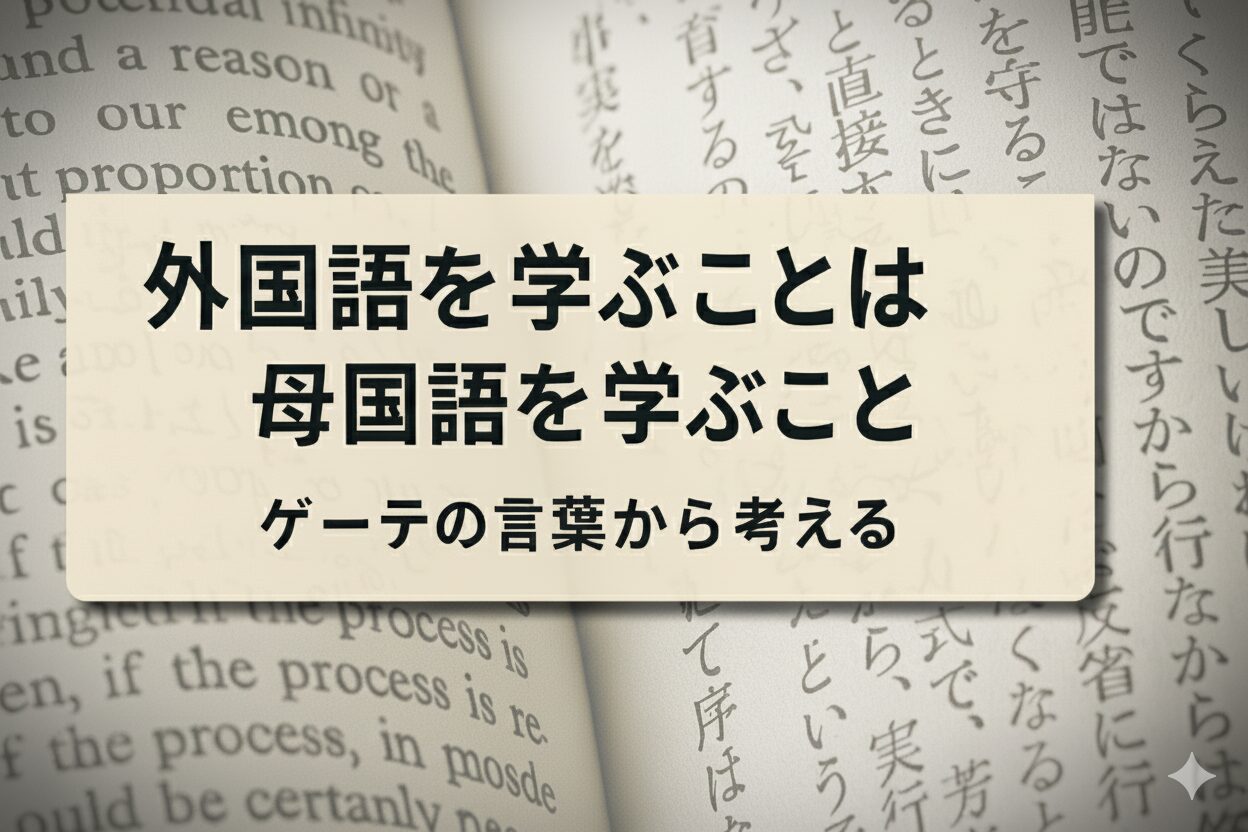
言語は比較してこそ見える
ゲーテの名言に「外国語を知らない者は、自国語も知らない(Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.)」というものがあります。
一見すると逆説的に思えるこの言葉は、言語学だけでなく教育や文化の観点からも示唆に富んでいます。この記事では、この言葉を手がかりに、母国語と外国語の学習の関係を考えてみます。
母国語は「無意識の言語」
母語は私たちにとって「空気」のような存在で、母国語を「学んだ」という感覚はあまり持っていません。乳幼児期に自然に習得し、意識することなく使っているからです。ところが、空気を意識できないのと同じで、母語もまた「比較対象」がなければその特徴に気づきにくいのです。
例えば、日本語では主語を省略することが多いですが、英語を学ぶと「必ず主語を明示する」構造との違いに気づきます。そこで初めて、「日本語は文脈依存が強い言語なのだ」という母語の特徴を自覚できるのです。
また母国語では、文法構造や語彙の仕組みを意識する機会が少ないため、「使えるけれど説明できない」という状態が発生しやすいという事態にも気づくことでしょう。
外国語学習は「母国語の再教育」
言語学習は単なるコミュニケーション手段の習得ではありません。むしろ、自国語を客観的に見つめ直し、論理的に説明できる力を養う営みでもあります。
言語は比較してこそ見えてきます。なぜなら、外国語を学ぶ過程では、必ず「翻訳」や「比較」が生じるからです。
- 英語の「I miss you」を日本語に訳すと「あなたがいなくて寂しい」になる。この時、感情の表現方法が文化によって異なることに気づく。
- ドイツ語の格変化を学ぶと、日本語の「助詞」が持つ役割がより鮮明になる。
- フランス語やスペイン語の性別名詞を知ると、「日本語には名詞の性がない」という事実に改めて驚く。
- 中国語や韓国語の語順を学ぶことで、日本語の「主語省略」や「曖昧さ」の文化的背景が浮き彫りになる。など
このように、外国語の仕組みを知ることで、無意識に使ってきた母語の特徴や可能性が相対化できます。
その結果、母国語での思考力や表現力も向上し、翻訳を通じて日本語のニュアンスを豊かに捉え直したり、ライティングやスピーチにおける言葉の選択が洗練されていくのです。
ゲーテの言葉の現代的意味
ゲーテがこの言葉を述べた18~19世紀は、国民国家が形成され、ドイツ語の標準化が進んでいた時期でした。多言語環境の中で、自国語をいかに意識的に捉えるかが重要なテーマだったのです。ゲーテ自身もフランス語、イタリア語、ラテン語に精通しており、それらとの比較から「母語を理解するには他言語が不可欠だ」という実感を持っていたのでしょう。
そして現在、グローバル社会においてこの言葉はさらに重みを増しています。外国語を学ぶことは単なるスキル獲得にとどまらず、自国語の奥行きを再発見する行為でもあり、母語理解の深化は、アイデンティティの確立にもつながります。
つまり、両者は対立関係ではなく、相互補完的な関係なのです。
結局のところ、外国語と母国語は車の両輪です。外国語を学ぶことで母語が深まり、母語を磨くことで外国語の理解も深まります。片方だけを鍛えてもバランスが悪く、言語的な思考力全体が伸びません。
今日に生きるメッセージ
ゲーテの言葉は「外国語を学べ」という単なる語学学習のすすめだけに留まらず、「自分を知るために他者を知れ」という普遍的な人間へのメッセージでもあります。
他者を知ることは
- 比較による理解
他者の価値観や行動様式を観察することで、「自分が当然と思っていること」が実は文化や環境に依存していることに気づけます。
→ つまり、他者の「違い」が、自分の「当たり前」を浮き彫りにする。 - 鏡の役割
人との関わりは、自分の反応や感情を映す鏡になります。誰かに対してイライラする、自分を守りたくなる、尊敬する──そうした感情を辿ると、自分の価値観や弱点、欲求が見えてくる。 - 可能性の拡張
他者の生き方や選択を知ることは、自分がまだ知らない可能性の地図を広げることにもつながります。「あ、そんな考え方があるのか」と知ることで、自己の選択肢を増やせる。
・・・言語にも置き換えられますね。