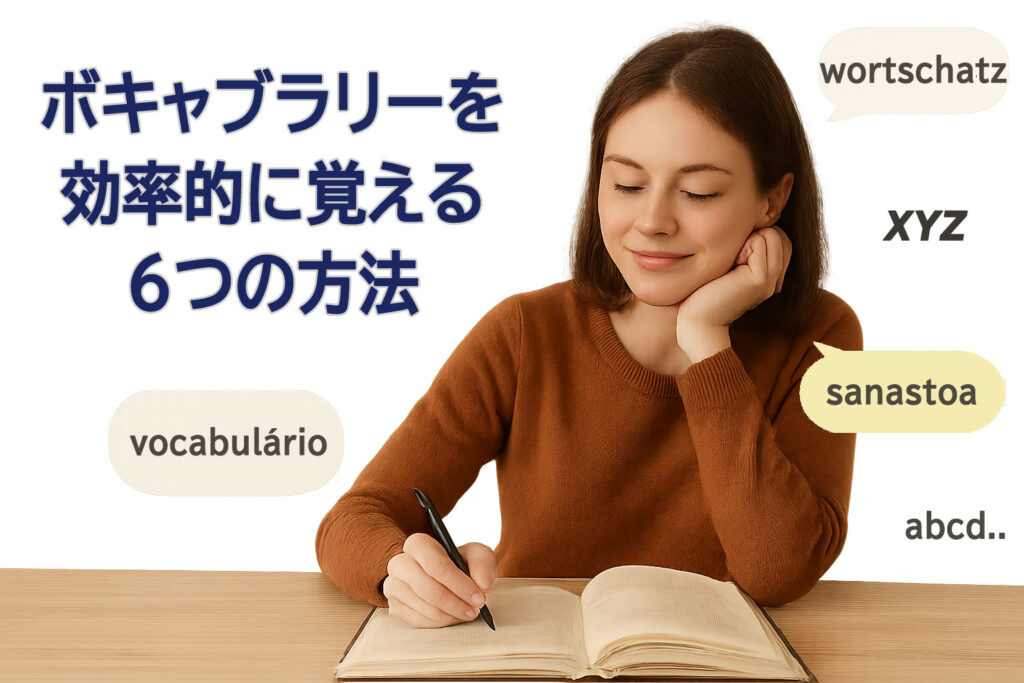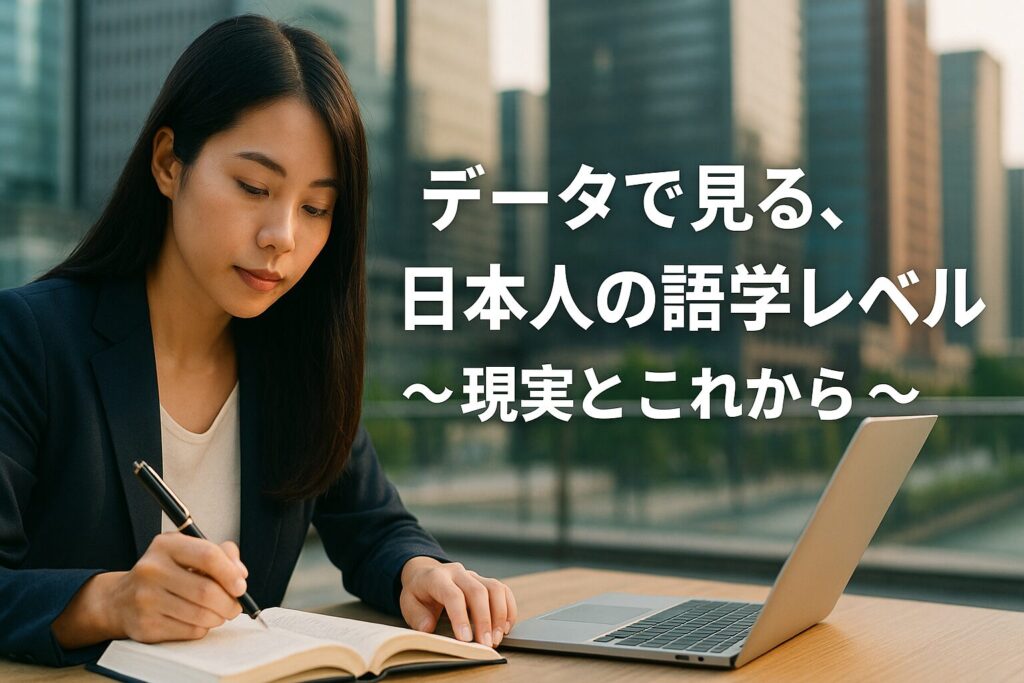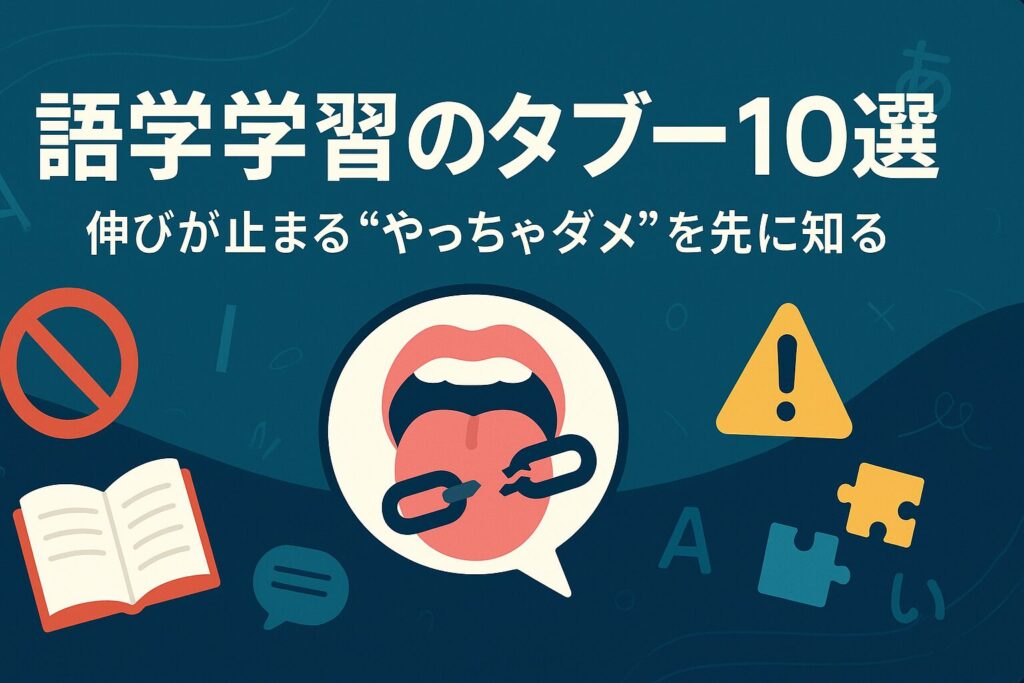データで見る、日本人の語学レベル ~ 現実とこれから ~
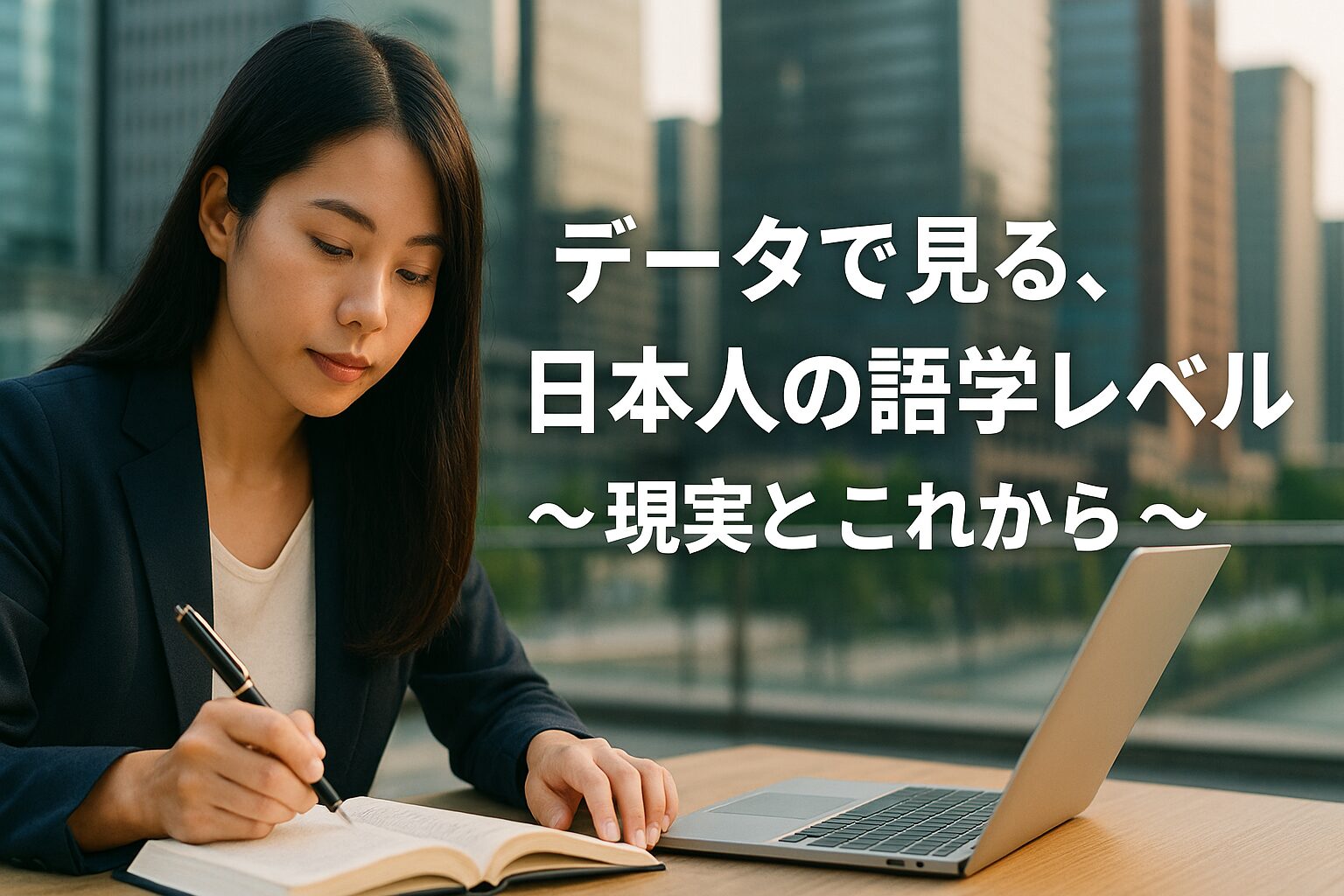
国際化と日本人──語学レベルから見える可能性と壁
「日本人は英語が苦手」「読み書きはできるけれど話せない」とよく言われますが、実際のところはどうなのでしょうか?
今回は、国際的なランキングや統計データをもとに、日本人の語学力の現状を読み解いていきます。
世界から見た「日本の語学力」は?
英語能力を評価する国際的な指標を見てみましょう。日本の英語力は世界では何位に位置していて、どのくらいのレベルなのでしょうか。
2024年の国際的な英語能力指標「EF English Proficiency Index(EF EPI)」によると、日本の英語能力ランキングは前年の87位から5ランクダウンし世界92位(116の国・地域の下位約20%)。アジア圏ではシンガポール3位や韓国50位よりはるか下で、「低い英語能力レベル」と評価されています。
EF English Proficiency Index(EF EPI 2024)
- 世界ランク:92位 / 116カ国中
- アジア圏:16位 / 23カ国中
- レベル:「低い(Low proficiency)」に分類
| 国 | ランキング(アジア圏内) | レベル |
|---|---|---|
| シンガポール | 3位(1位) | 非常に高い |
| フィリピン | 22位(2位) | 高い |
| マレーシア | 26位(3位) | 高い |
| 香港(中国) | 32位(4位) | 中程度 |
| 韓国 | 50位(5位) | 中程度 |
| ネパール | 56位(6位) | 中程度 |
| … | … | … |
| 日本 | 92位(16位) | 低い |
2024年のデータでは93位以降は「非常に低い英語能力」と評価されています。このまま語学力の衰退が続けば、日本は「非常に低い英語能力」の国と評価されるかもしれません。
日本国内のテストスコア傾向
TOEIC L&R(リスニング&リーディング)
日常生活やグローバルビジネスにおける生きたコミュニケーションに必要な「英語で話す・書く能力」を測定するテストTOEICの世界平均点数は約705点(グローバル企業内の受験者含む)のところ・・
- 日本国内平均点数は約590点(2024年最新データ)
- 社会人層でも600点台に届かないケースが多数
英検・CEFRとの対応(文部科学省資料)
- 日本の中学卒業レベル:CEFR A1相当
- 高校卒業でも:A2〜B1が一般的
- 国際的なビジネスシーンではB2以上が望まれるが、到達者は一部に限られる
※CEFR(セファール)って?
ヨーロッパ基準の語学レベル指標で、A1(初級:入門レベル)〜C2(上級:マスターレベル)まで6段階評価。
こんなに学んでいるのに何故?
小さいころから英会話教室に通う児童も増え、小学校から英語教育も始まりました。(2020年度改訂 学習指導要領ベース)日本人は在学中、平均6〜12年間英語を学んでいますが、“日常会話に苦労する”レベルにとどまっています。早いうちから「英語に慣れ親しむこと」ができる環境が整ってきたのに、何故こんなに「英語ができない国」という評価なのでしょうか。考えられる4つの要因について解説します。
1. 教育制度の構造的問題
- 文法・読解偏重の教育
中学・高校では受験対策として「文法」や「読解」が重視され、実践的な英会話や発音練習の機会が極端に少ない。 - スピーキング評価の欠如
センター試験(共通テスト)でも、リスニングは導入されてもスピーキングの評価はほぼ皆無。
2. 英語に触れる環境の少なさ
- 日常生活で英語が不要
日本語だけでほとんどのことが済むため、英語の必要性を感じにくい社会的環境がある。 - メディアの吹き替え文化
海外映画や番組も吹き替えが主流で、英語に生で触れる機会が乏しい。
3. 心理的ハードルと文化的要因
- 「間違えること=恥ずかしい」というシャイ文化
完璧主義や同調圧力が強く、「ミスを恐れて発言しない」傾向が強い。 - 「脱!完璧主義」。話す前に「正解を探す」癖を捨てよう
自然な会話よりも、正しい文法や表現・発音を過剰に気にするため、言葉が出にくくなる。
4. 教員の英語運用能力の差
- 英語教員自身が英語を実践的に使いこなす機会が乏しく、結果的に教育内容も理論偏重になりがち。
英語力向上のための効果的な対策 ~ 「知識重視」から「運用重視」へのシフト
1. カリキュラムの実践重視改革
- 小中高のスピーキング・リスニング比率を増やす
毎授業で1人1回は話す機会を設定するなど、「声に出す」「聞き取る」習慣を制度的に作る。 - CEFRベースの評価導入
ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)に基づいた評価で、「使える英語力」重視へ転換。
2. 英語への接触頻度を高める
- 英語音声+字幕のメディア利用
NetflixやYouTubeなどで、英語音声+日本語字幕 → 英語字幕 → 字幕なしの段階的アプローチ。 - SNSやアプリでの英語発信
X(旧Twitter)やYouTube Shortsで「英語で発信」する場を増やす。失敗してもOKな空間が重要。
3. 心理的安全性の確保
- 「間違えることは恥ずかしくない」の文化づくり
英語の授業や学習コミュニティで、「失敗=学び」という価値観を共有する。「間違えても伝える」を当たり前にする文化へ - ペアワーク・グループディスカッションの導入
一人で話すのではなく、仲間と一緒に英語を使う体験を重視し実践経験を増やす
4. 教師トレーニングの強化
- 教員向けの実践英語研修
海外研修・ALTとの共同授業・オンライン英会話活用などを組み合わせ、「教える英語」から「使える英語」へ。 - 語学教育プラットフォームの導入
ALTISSIA (アルティシア)は、アカデミックな専門家集団が作り上げた本格的な学習メソッドを提供しています。教師へのサポートも充実!
5. AIやICTの活用
- 音声認識・発音診断アプリ
例えばELSA SpeakやYouGlishなどを使って、自習でも発音やフレーズのフィードバックが得られる。 - AI英会話との対話練習
ChatGPTのようなAIを活用して、無限に話す練習ができる安全な場を提供。
データが示すのは「希望」
日本人の英語力が低いのは「能力不足」ではなく、環境と学習機会の非対称性による構造的な問題です。そして、近年の教育改革やテクノロジーの進化により、その改善の道筋は明確になっています。つまり、ここからはポテンシャルしかない!とも言えるのです。
日本人は本当に「語学が苦手」なのか?
答えは「No」
日本人の語学レベルが国際的に見て「高くはない」のは事実です。でも実は、日本人の語学学習者は文法や語彙の知識量は世界でもトップクラス。これからは、読み書きの強さを会話に活かす訓練へとシフトしましょう。
語学力は“運動神経”と同じ。座学だけで上手くなることはありません。
実際に声を出し、相手に通じた・通じなかったというリアルな経験の積み重ねが必要なのです。
そして語学はスキルです。筋トレと同じで、やれば伸びる。やらなければ現状維持(あるいは退化)。
「使える語学力」を手に入れるのに、遅すぎるなんてことはありません。
英語力は給与や昇進に直結する企業が増加している時代。英語を「勉強」ではなく「使うもの」と捉えるマインドチェンジと、それを支える仕組みづくりがカギになります。
語学学習の近道
語学は「使いながら伸ばすもの」。これまでの「試験英語」とこれから必要な「実用英語」のギャップを埋めていきましょう。
- 「TOEICは高得点でも、会話になると詰まる」
- 「留学に興味はあるが、英語力に自信がない」
- 「英語でメールは書けるが、電話やミーティングは怖い」
Don’t be shy! It’s okay to make mistakes.
CEFR by ALTISSIA の語学スキルテストで、自分のポテンシャルに気づく!
苦手な分野は伸ばすだけ!4技能語学レベルチェックで課題を探ろう
こんな教材が欲しかった!
学生の語学力を実践的に高めたい教育者の方
グローバル化を進めたい企業・教育機関の方